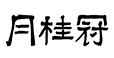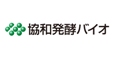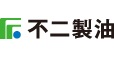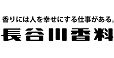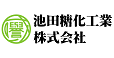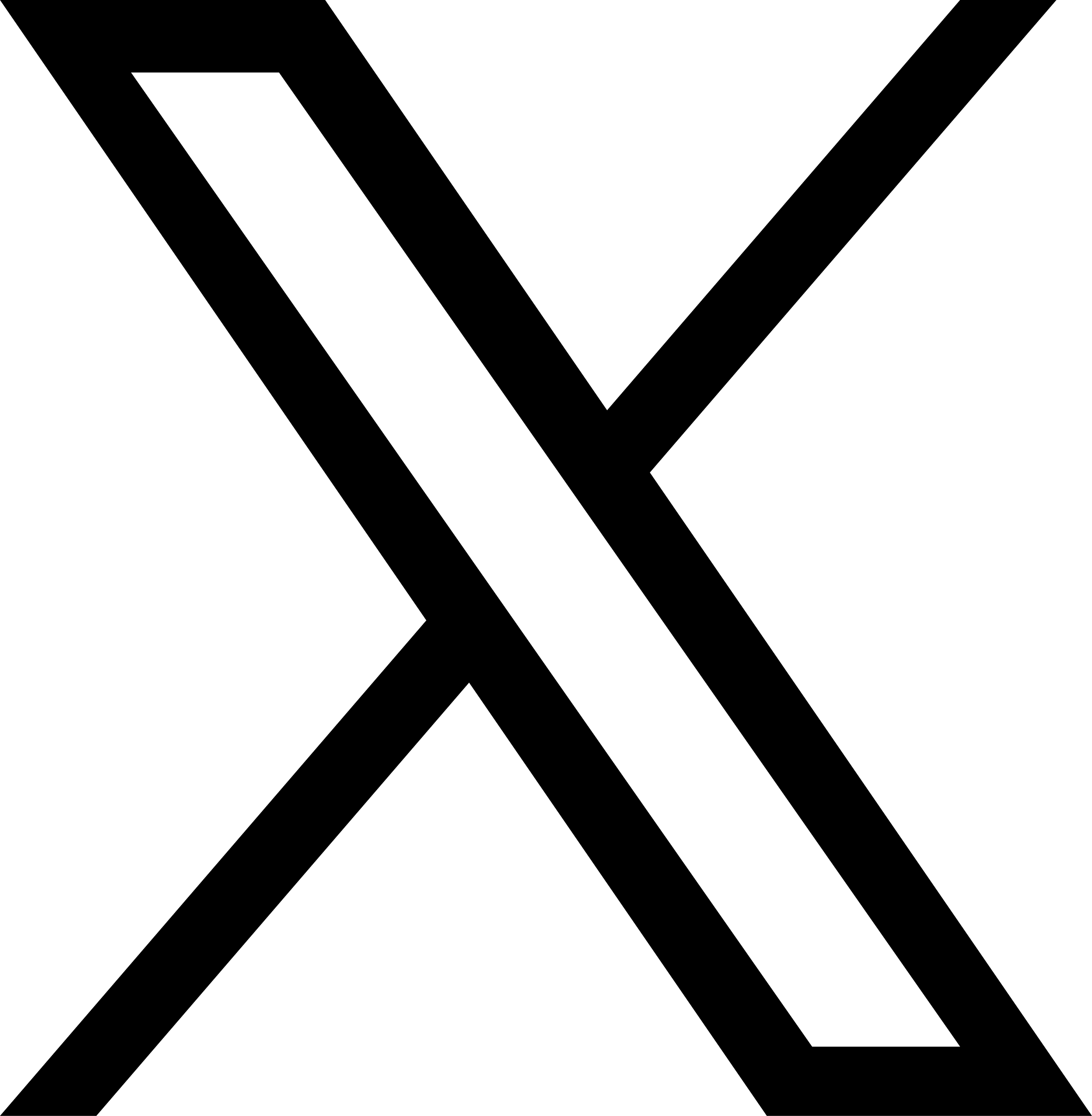2025年度産学官学術交流フォーラム
報告
2025年3月6日(木)、日本農芸化学会2025年度大会(札幌)において、産学官学術交流フォーラムを開催しました。
第一部では第20回から第22回の農芸化学研究企画賞受賞者8名の先生による企画発表および中間・最終報告、第二部では「農芸化学が拓く希望の食卓」と題し、環境や健康に配慮した持続的な未来の食卓に関しユニークかつ最先端の取り組みをされている6名の講師による講演会を行いました。全体を通して300名を超える非常に多くの方々にご参加いただきました。ご講演者の皆様およびフォーラムに参加していただいた皆様にあらためて御礼を申し上げます。
以下、フォーラムについて簡単にご報告致します。
第一部:農芸化学企画賞受賞者報告会
第一部では、第20回から第22回の農芸化学研究企画賞受賞者8名の先生による企画発表および中間・最終報告が行われました。それぞれの先生方から、これまでの研究背景や独自の着想に基づいた多岐にわたる企画内容とその進捗が報告されました。実用化を目指した研究が着実に進められていると同時に、その研究過程で新たな研究シーズも多く生まれている印象を受けました。いずれのご発表も、今後の展開が非常に楽しみな内容でした。
第22回受賞者による受賞企画報告
- 「植物代謝物が触媒する光依存的二重結合異性化メカニズムの解明と応用」
瀬戸 義哉 氏(明治大学農学部) - 「近接依存性標識法を基盤とする細胞選択的な集密分子修飾と応用」
田中 知成 氏(京都工芸繊維大学繊維学系) - 「AIを用いた次世代創農薬」
村瀬 浩司 氏(横浜市立大学生命ナノシステム研究科)
第21回受賞者による中間報告
- 「減算的菌叢改変技術を活用した次世代プロバイオティクスシード微生物の発掘」
岡野 憲司 氏(関西大化学生命工) - 「糖鎖を標的とした新興感染症治療薬リードの開発」
中川 優 氏(名古屋大糖鎖生命コア研究所)
第20回受賞者による最終報告
- 「翻訳を促進する新生ペプチドの探索とタンパク質生産への産業応用」
加藤 晃代 氏(名古屋大学大学院生命農学研究科) - 「産業応用を目指した肝臓オルガノイドの新規培養技術開発とヒト肝臓生理機能の解明」
高橋 裕 氏(東京大学大学院農学生命科学研究科) - 「ネコのマタタビ反応の研究から着想した蚊の忌避剤の開発」
西川 俊夫 氏(名古屋大学大学院生命農学研究科)


第一部の様子
第二部:講演会「農芸化学が拓く希望の食卓」
第二部では、「農芸化学が拓く希望の食卓」と題した講演会を開催しました。人間と環境の相互作用を理解し持続可能で健康な地球と人のあり方を創出するという「プラネタリーヘルス」という概念から、実例としてフードロス削減技術や持続可能な食料供給技術、開催地である北海道を拠点とした新規事業、疾患や体質によらず同じ食卓を囲める技術、災害時の食と健康の確保についてなど、所属や分野を超えた最新の取り組みをご紹介いただきました。地球環境や健康に配慮した持続的な未来の食卓の実現に向けて、現状の確認や問題意識の共有、ひいては農芸化学分野から何ができるかを考えるきっかけの場となりました。
- 「東京大学ゲートウェイキャンパス:プラネタリーヘルスを目指した新しい産学協創の形」
五十嵐 圭日子 氏 (東京大学大学院農学生命科学研究科)
五十嵐先生からは産学協創へのあり方について問題提起頂き、アカデミアと企業がwin-winでサステイナブルな協創関係の構築、そして純粋にサイエンスを突き詰められる環境づくりとして、Planetary Health Design Laboratoryについてご紹介頂きました。当該研究所はJR東日本、東大、パスツール研究所を中心に、生命科学研究に加えて、人材開発やスピンオフの支援事業等を行い、プラネタリーヘルスの実現を目指すとのことです。非常にスケールが大きく、夢のあるご講演で今後の進捗に期待致します。(報告、さんわか:矢野) - 「植物活性イノベーションで実現する「世界の食卓の未来」、「新しい農業の未来」」
上籔 寛士 氏(アサヒバイオサイクル株式会社 サステナビリティ事業本部)
持続可能な農業と食料安全保障を目指した「ビール酵母で育てる畑のお米チャレンジP」について紹介いただきました。節水型乾田直播栽培により水管理を不要にし、それによりメタン発生も抑制する次世代の農業技術です。独自に開発したビール酵母を活用し、お米の収量増加と安定化を達成されています。ビール酵母の種子処理と播種後の4回の葉面散布というシンプルな方法で同プロジェクトを他県でも成功させており、2050年に起こり得ると警鐘されている世界的な食料危機を防ぐ革新的なアプローチだと感じました。(報告、さんわか:白石) - 「大学との共同開発技術の社会実装~“エレキソルト”開発と減塩推進の取り組み~」
佐藤 愛 氏(キリンホールディングス株式会社 ヘルスサイエンス事業部)
佐藤先生からは、電流を用いたイオン性成分の動きを調節することにより、塩味等の増強効果を得られるデバイス「エレキソルト」についてお話いただきました。日本人の食事において食塩摂取量の低減は課題ですが、普段の味付けを変えることは容易ではなく、先生ご自身も減塩食を3ヶ月続けたところ、食欲自体がなくなってしまったそうです。そうした経験から、他分野の明治大学との産学連携により電気味覚技術を用いた減塩デバイスの開発につなげられてきました。さらに、社内の制度を活用して、技術の探索から企画を提案、さらに製品化に至ったという、社会実装までの流れもご紹介いただきました。現在、エレキソルトは一般販売のほか、自治体や企業で導入して実証実験が行われており、料理雑誌とのレシピ開発なども進められているとのことで、今後さらに社会全体で減塩習慣が普及していく助けになると強く感じました。(報告、さんわか:石川) - 「ゲノム編集生物の社会実装―低アレルゲン鶏卵開発からの考察―」
堀内 浩幸 氏(広島大学大学院統合生命科学研究科)
ゲノム編集技術によって開発された、オボムコイドを含まない鶏卵についての講演を伺いました。オボムコイドは他のアレルゲンと違い、熱や酵素処理では分解されず、加工食品にも残るため、低アレルゲン卵の誕生は非常に画期的です。社会実装に向けては、知的財産の整理、安全性評価、生産体制の整備、各省庁への届出などが必要ですが、産学官のチームが一丸となって取り組んでいます。すでに安全性や有効性、加工適性が確認され、臨床研究も進んでいます。さらに、コストの課題やゲノム編集技術に対する正しい理解の普及にも丁寧に対応されており、卵アレルギーの方が安心して加工食品を楽しめる未来が、着実に近づいていると感じました。(報告、さんわか:永嶌) - 「特殊ミルク供給事業と私たちの取り組み」
◯津田 宗哉 氏(森永乳業株式会社 健康栄養科学研究所)、井田 博幸氏(代謝異常児等特殊ミルク供給事業 安全開発委員会)
先天性代謝異常症やアレルギー疾患などの治療に必要不可欠な「特殊ミルク」について、ご講演いただきました。独自の製造技術により、乳タンパク質を加水分解し、原因物質を選択的に低減させたミルクで、遊離アミノ酸の混合粉末よりも風味が良好な品質設計をされているとのことでした。分析技術による代謝異常の可視化や成人患者数の増加により、特殊ミルクの需要は増加する一方で、生産体制の制限等でメーカーへの負担も大きいことを知り、産学官による連携や協力によるサステナブルな事業活動が重要であると感じました。(報告、さんわか:山中) - 「個別栄養最適食「AI食」で未来のウェルビーイングを実現」
小山 正浩 氏(株式会社ウェルナス)
個人に適した食事を提供する「AI食」に関してご講演頂きました。AI食は、開発者ご自身の食の大切さを感じたご経験から生まれたサービスで、日々の食事と体のデータを解析することで、体に影響を与える栄養素を特定し、増やすべき、または減らすべき食事を提案することができます。これまでの実例として、カロリーを変えずに体重減少を実現することに成功しており、80%のユーザーがこの効果を実感しているとのことです。AI食による提案は、体重の減量だけではなく、血圧を下げたいならば血圧データを記録するなど、日々記録するデータによって様々なものに適応が可能ということで、多くのユーザーに需要があるサービスであり、今後多くの方が利用されるだろうと感じるご講演でした。(報告、さんわか:堀)


第二部の様子
ご多忙の折、ご講演を引き受けてくださいました講演者の皆様、発表者の先生方、広報にご尽力くださいました皆様、そして本フォーラムにご参加いただきました多くの皆様にあらためて御礼申し上げます。来年度以降も、本フォーラムが更なる産学官交流の促進に寄与し、農芸化学分野における研究・事業化の発展に帰することを願います。
なお、第11期のさんわかは本フォーラムが最後の活動となりました。これまでご協力いただいた皆様に厚く御礼申し上げます。4月より活動を第12期に引き継ぎ、更なる産学官交流の推進を目指し活動を続けて参ります。今後とも、さんわかの活動にご協力・ご参加いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。(さんわか世話人:加藤、永嶌)
概要
2025年度産学官学術交流フォーラムにおいては、農芸化学企画賞受賞者による受賞・中間・最終報告に加え、「農芸化学が拓く希望の食卓」と題した講演会を企画しました。人間と環境の相互作用を理解し持続可能で健康な地球と人のあり方を創出するという「プラネタリーヘルス」という概念から、実例としてフードロス削減技術や持続可能な食料供給技術、疾患や体質によらず同じ食卓を囲める技術、災害時の食と健康の確保についてなど、所属や分野を超えた最新の取り組みをご紹介いただきます。
地球環境や健康に配慮した持続的な未来の食卓の実現に向けて、現状の確認や問題意識の共有、ひいては農芸化学分野から何ができるかを探求するきっかけの場としたいと願っております。
第一部では、第20回から第22回「農芸化学企画賞」受賞者による報告会を行います。
第二部では、環境や健康に配慮した持続的な未来の食卓に関しユニークかつ最先端の取り組みをされている6名の講師を招待し、その取り組みについてご講演いだきます。
日本農芸化学会2025年度大会(札幌)参加登録者以外も参加可能ですので、奮ってご参加いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
| 日時 | 2025年3月6日(木)13:00~18:00(大会3日目) |
|---|---|
| 会場 | 札幌コンベンションセンター A会場(特別会議場、1階) |
| 主催 | 日本農芸化学会「産学官学術交流委員会」 |
| 企画 | 日本農芸化学会「産学官学術交流委員会」「産学官若手交流会(さんわか)」 |
| 参加費 | 無料 |
| ポスター | 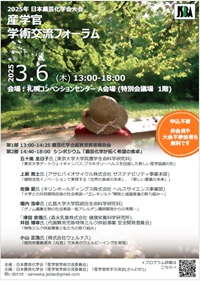 2025年度産学官学術交流フォーラム ポスター(PDF) |
| プログラム | ■第一部:「農芸化学企画賞受賞者報告会」(13:00~14:25) 13:00~13:05 開会の挨拶 <第22回受賞者による受賞企画報告> 13:10~13:15 13:15~13:20 <第21回受賞者による中間報告> 13:30~13:40 <第20回受賞者による最終報告> 13:55~14:10 14:10~14:25 |
■第二部:講演会「農芸化学が拓く希望の食卓」 (14:40~18:00) 14:40~14:45 14:45~15:15 15:15~15:45 15:45~16:15 16:15~16:25 16:25~16:55 16:55~17:25 17:25~17:55 17:55~18:00 閉会の挨拶 |
|
| 要旨集 | 要旨集(PDF) ※要旨集はパスワードを設定しております。ご参加者様には当日会場にてパスワードをご案内いたします。 |