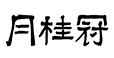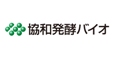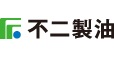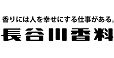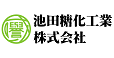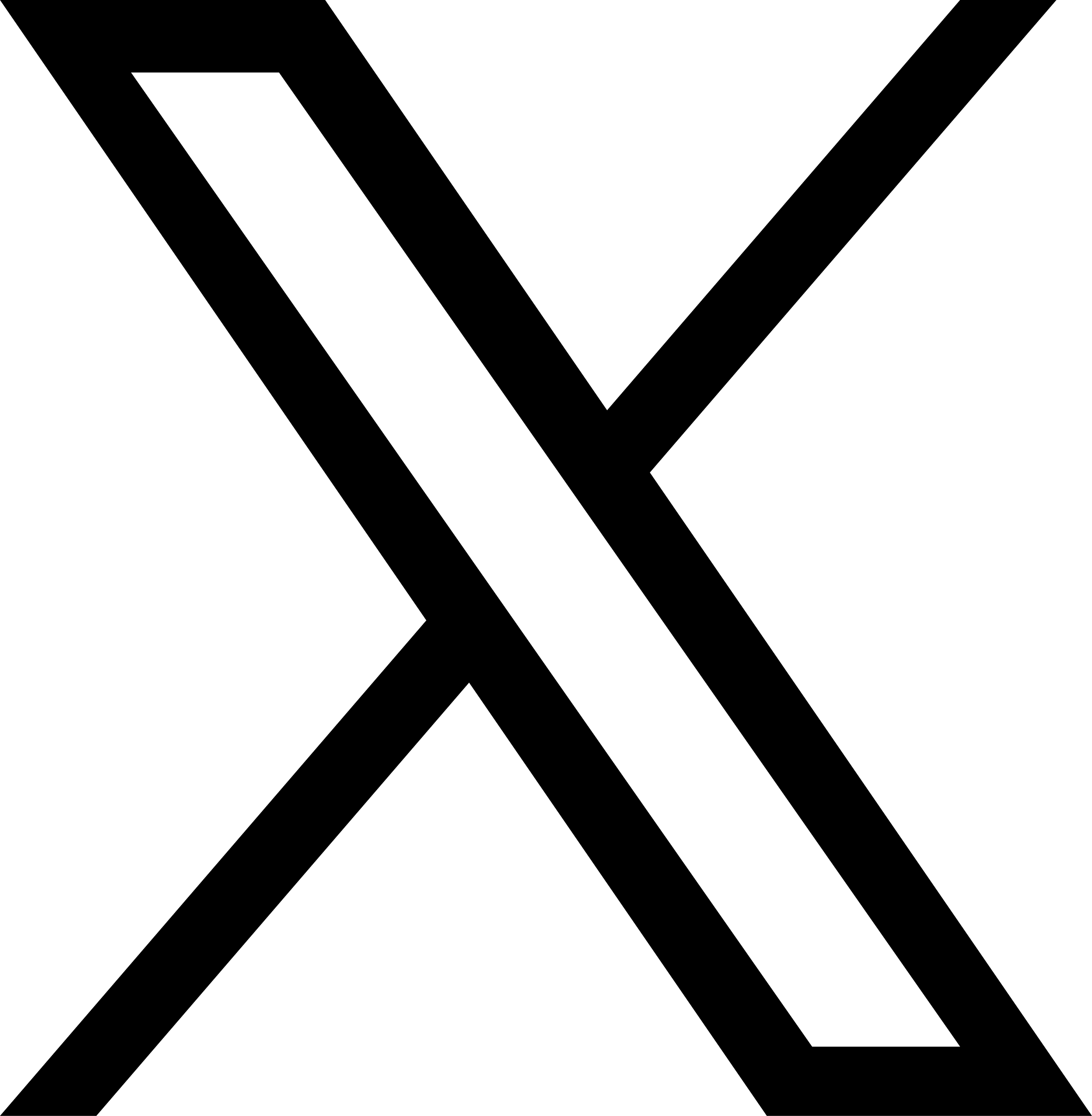第67回 出前授業 実施報告
| 団体名 | (東京都)都立両国高等学校附属中学校 |
|---|---|
| 開催日 | 2023年2月24日(金) |
| 場所 | 都立両国高等学校附属中学校(墨田区江東橋1丁目7番14号) |
| 授業の名称 | 酵母、発酵の魅力とそれに魅せられた研究者たち |
| 講師 | 吉田 聡 氏(キリンホールディングス(株)R&D本部飲料未来研究所 リサーチフェロー) |
| 聴講者 | 3年生110名 |
| 報告 | 普段口にしている発酵食品の仕組みや、酵母について、詳しくは知りませんでした。今回の講演では、難しい内容にも関わらず吉田先生がたくさんの例をスライドや動画を交えながら、分かりやすく丁寧に説明をしてくださいました。そのおかげで、生徒たちは楽しみながら、酵母の力、奥深さを知ることができました。講演前は、「酵母はただ発酵させて、食べ物本来とは違う味や、臭いにするもの」だと考えている生徒もいましたが、実際は、発酵と腐敗の違いが、微生物が活動するところまでは同じで、そこから微生物の生命活動を利用して人間にとって役立つか、役立たないかの違いだったこと。さらに、食べ物に限定されるものではないことなどを知りました。一例として、ナタデココに含まれるセルロースを乾燥させて、ディスプレイ等、工業的な利用が検討されていたり、グルコースからピルビン酸を経由してL-乳酸を作り、バイオプラスチックを生産したり、何気なく食品として食べている酵母が、研究によって、実は私たちの暮らしを支えていること、酵母の面白さ、不思議さに気づかされました。 KIRINでの具体的な仕事内容を聞き、文系・理系共に様々な仕事が集まっていて、研究に励む人、工場で働く人、パッケージをデザインする人など、一口に会社といっても、数えきれない程の職種と人々が、1つ製品に関わっていることを再認識できました。
講師の吉田先生からは、酵母、発酵の魅力だけでなく、今後の生き方に役立つ考え方を教えていただきました。「自分から進んで挑戦することが成功への第一歩となる」など、多くの金言に触れ、生徒一人一人にとっての「学び」「気付き」がある、実り多い講演会となりました。研究者として、社会人の先輩として、本校生徒のために情熱をもってご講演いただきまして、誠にありがとうございました。 |
授業風景

生徒さんの感想
- 「社会にとって必要かどうか」を行動の指針にしているお話を聞いて、まだ「社会貢献」という大きな目標は掲げられなくても、私も何か信念をもって行動するようにしたい。
- 吉田先生が大学受験をするときや、就職するときに、どんなことをやりたいか明確には定まっていなかったという話を聞いて、驚きました。私はまだ将来何をしたいかが決まっておらず、少しずつ焦り始めていました。明確な将来の夢を定める、ということを学生時代に果たさなくても、研究者として、やりがいのある仕事に出会い活躍されている人がいると知って、安心しました。同時に、今のうちに様々な経験を積んで、様々な分野に興味をもっていきたいと思いました。
- 吉田先生は、その先までを見据えて、あくまで可能性をつぶさないような選択をしていた、とおっしゃっていました。私は現在、将来の夢ややりたいことなどが明確に決まっていません。今後の科目選択や大学の学部選びなどの際の参考にさせていただきたいと思います。
- 将来のことで不安に思っていたことに対して、こういう道もあるのだ、ということに気づかせていただきました。また、理系の勉強が社会に貢献できると知りました。
- 興味のあることは、興味のあるままにするのではなく、とことんつきつめて、自分の得意な分野にしていきたい。
- 倫理感について、倫理的に道徳的にマナーを守るというのは、人それぞれボーダーラインが違うから難しい。だからこそ、多種多様なものの考え方を持った人たちと対話していくことが大切。
- 会社の職種のお話では、パッケージングなど、理系でこんなお仕事があるのかという発見が多くあり、もっと広い視野で職業を考える必要があると思った。
- 研究のポイントは、「良くないところをなくす」ということを意識するとおっしゃっていました。これは、私がやっている水泳にも同じことが言えるので、とても共感することができました。
- 私は、一度失敗したらとても落ち込んでしまい、なかなか次の一歩を踏み出すことができなかったため、知らず知らずのうちに成功のチャンスを逃してしまっていたかもしれない。これからは、教えていただいた金言通り、スポーツや勉強に励んでいきたい。
- 吉田先生のような方も「失敗は、たくさんする」とおっしゃっていたので、背中を押してもらった気がします。
- 最後に、「研究や勉強は、やれるときにやる」のが良いとおっしゃっていました。今、自分は何のために勉強をしているのか分からず、なかなかモチベーションが上がらない時期もありました。しかし、今頑張ったことは必ず将来に役立つと思うので、努力を怠らず、誠心誠意勉学に励んで行こうと思いました。
- 研究者として成功するか否かは、日常にぶらさがっているチャンスに反応する嗅覚次第だと感じました。そのためには、日頃、社会情勢にアンテナをはり、多種多様な知識をつけておくことが大事だと思いました。
- 世の中に役立つものは、身近に隠れていることを知り、そのための準備をいつでもしておくことの大切さがよく理解できました。
- 人生において「絶対に〇〇だという思い込みは、自己の成長を妨げる」と思うので、そういった思い込みは捨てて、失敗することを恐れずに、また、成功するまであきらめずに、やりたいことと向き合っていきたい。